自宅で介護を行う上で気を付けなければいけないこととして、これ以上様態を悪化させないようして、介護度を上げないようするということがあります。つまり介護予防です。
そこで今回は、私たちでも簡単にできる身近な介護予防の実践方法をいくつかご紹介したいと思います。

自分で出来ることは自分でやってもらう
介護とは、どうしても無理なことだけをサポートするようにした方が本人のためになります。
介護の大きな目的は現状維持。または、心身の機能を回復させて高齢者の自立を助けることです。ですので、決して楽をさせることや寝かせておくことが介護ではありません。
「寝たきり」と「寝かせきり」は全然違います。私が見てきた中には、家族が過保護になりすぎて、本人のやろうという意欲が失われているといった場合がとても多かったです。
心配になる気持ちはもちろん分かりますが、時に厳しくすることで考える力や身体機能のお衰えを遅らせることができ、結果的に介護予防にも繋がります。

生活環境を変えて自立支援
自立のために無理をさせて怪我をしては本末転倒です。ですので、身の回りの生活環境を変えて本人が手を借りずとも日常生活出来るように工夫することも重要となってきます。
介護用のベッドを用意したり、廊下や階段には手すりを取り付けたり、車椅子でも移動しやすいようフローリングにするなど。時間がかかりゆっくりでも、こうした動作が自ら行うことが出来れば介護予防になるだけでなく、介護者の負担も軽減することができます。

本人に家事を手伝ってもらう
何もかも代わりにやってしまうのではなく、本人に家事を手伝ってもらうことも介護予防には効果的です。
炊事、洗濯、掃除など全てではなく各工程の一部といった感じで、少しずつでも家事を手伝ってもらうだけでも効果的です。とある介護施設でも、作業療法の一環として、簡単な家事を入居者にやってもらっているところも実際にあります。
またなかには、介護が必要になる以前と同じように家事を任されるということが、喜びや生きがいといった高齢者も少なくありません。
動作が遅かったり、間違うことがあるかもしれませんが、リハビリだと割り切って少しずつ出来る範囲で無理せず家事を手伝ってもらいましょう。

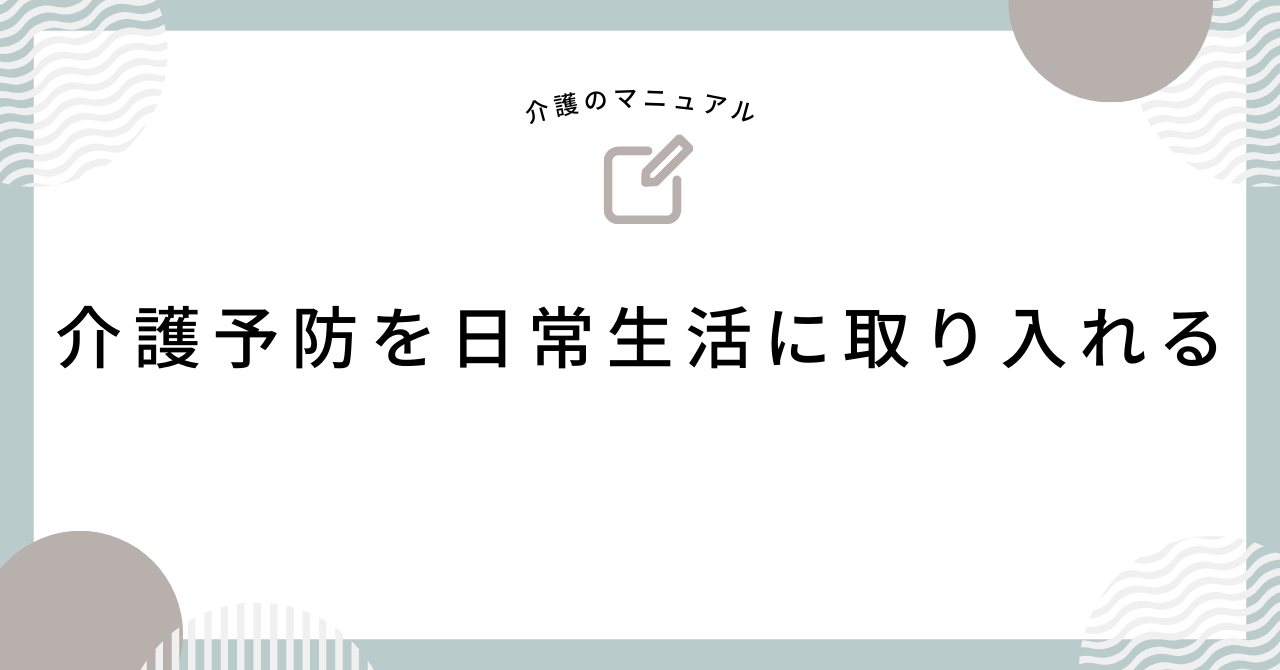

記事のコメント