介護は突然訪れる。今回はそのことが強く伝わってくる、こちらの記事をご紹介します。
骨粗しょう症がきっかけで認知症となり、ついには寝たきりとなった母を在宅介護する新田恵利さんのインタビューです。母が要介護4と認定され、どうしていいかわからなくなった時の心境を語っています。そして次のように後悔したそうです。
「親が元気なうちに、少しでも準備しておけばよかった」
読売新聞(ヨミドクター)
介護が必要になるきっかけは予測不可能
新田さんのお母さんが要介護状態となった原因は骨粗しょう症による背骨の圧迫骨折。何度か入退院を繰り返すうちに認知症を発症していました。これまでは入院しても数日で元気に退院していたので、認知症の症状が現れた当時はどうしていいかわからなくなったそうです。
何から行えばいいかわからず、とりあえず役所の福祉課に電話をしてからは、流れるように在宅介護に向けた準備が始まりました。地域包括支援センターへ連絡、担当のケアマネジャーの訪問、要介護認定の申請、介護ベッドの設置…。
ですが順調に進んだのは在宅介護の準備だけ。大変なのはその後からでした。
家族が全員協力して母を介護する
寝たきりになる前までは、自分のことは自分で出来ていたお母さんですが、食事から清拭、排便はおしめなのでその交換などを誰かが行う必要があり、新田さんと夫、そして新田さん兄の3人で協力して介護をしたそうです。
それぞれ仕事との両立を行いながらの介護。家族全員で協力して、自分がやれることをやる。家族介護には欠かせないことです。
介護は突然やってきます
新田さんのお母さんが介護状態になった流れは決してレアケースではありません。むしろ高齢者介護においては、怪我や病気がきっかけで要介護になってしまう流れがほとんどです。そういった時、家族を介護する準備ができていない時の負担は計り知れません。
介護は突然やってきます。親の衰えを頭では分かっても心が受け入れられない。気持ちの整理がつかないままに、介護生活を整えていかねばなりません。親がある程度の年齢になったら、介護の予備知識を仕入れて、勉強や準備をしておいた方がいいのだなあと切実に思いました。
読売新聞(ヨミドクター)
今回のインタビューを通じて新田さんは、介護に関する予備知識と事前準備の大切さを伝えてくれました。
介護を必要としていないのに、介護について勉強するなんて簡単なことではありません。ですが、生命保険に加入するように、親を持つ人であれば必ずしも訪れることです。
大まかで構いません。新田さんのように家族による在宅介護が始まるまでの流れを理解して、もしもの時に備えておきましょう。

85歳以上で2人に1人が介護が必要になる
| 年齢 | 要支援・要介護に認定される割合 |
|---|---|
| 40〜64歳 | 0.4% |
| 65〜69歳 | 2.9% |
| 70〜74歳 | 6.1% |
| 75〜79歳 | 13.8% |
| 80〜84歳 | 29.3% |
| 85歳以上 | 59.3% |
85歳以上になると、約2人に1人が要支援・要介護に認定されています。
介護が必要となった5大要因
1位:脳血管疾患
2位:認知症
3位:高齢による衰弱
4位:骨折・転倒
5位:関節疾患
※厚生労働省「平成25年度 国民生活基礎調査」
要介護状態になる原因は加齢だけでなはく、病気や事故が原因になることも。
平均寿命と健康寿命
| 性別 | 平均寿命 | 健康寿命 |
|---|---|---|
| 女性 | 86.61歳 | 74.21歳 |
| 男性 | 80.21歳 | 71.19歳 |
健康寿命とは健康な状態のこと。健康寿命を過ぎた後、平均寿命までは約12年。この12年は医療費や介護費用が急激に増えます。
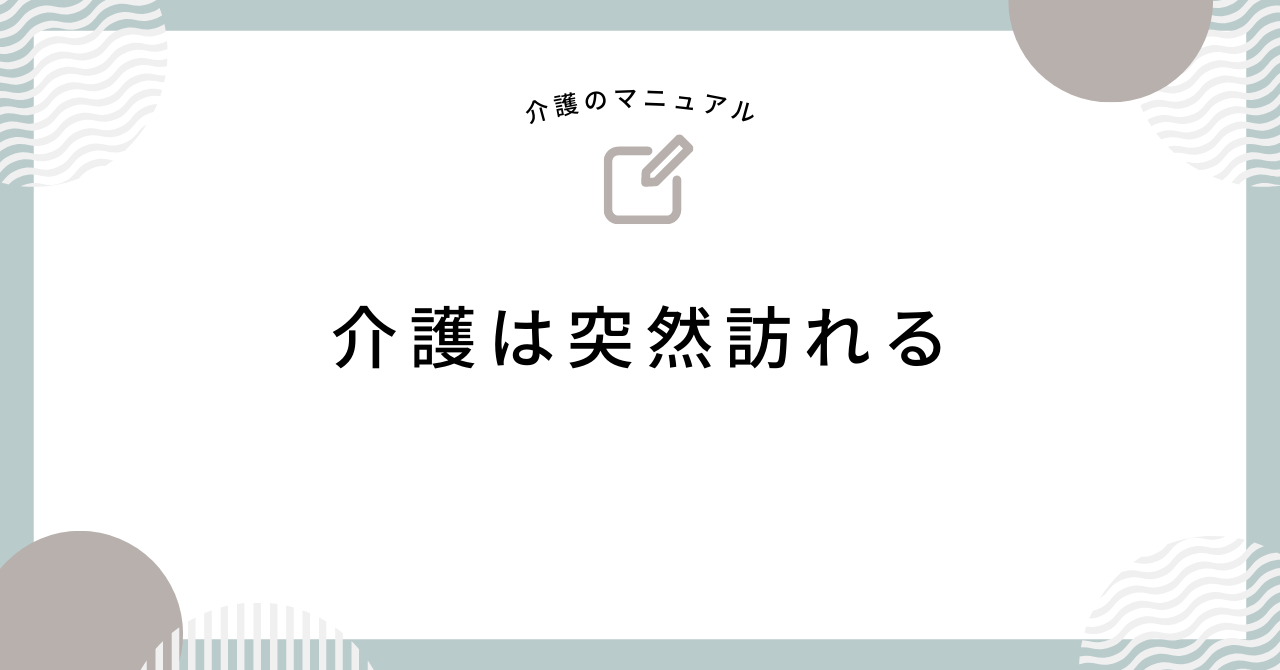

記事のコメント