高齢者が怪我や病気で病院に入院したら、同時に介護が必要になる可能性が極めて高くなるということも認識しておかなければなりません。
病気や様態にもよりますが、高齢者の入院期間は一般的に90日以内となっており、その間に家族は介護の準備をすることが大切です。
病院での治療が終わり退院後はどうするのか?自宅でリハビリや介護を行うのか?または介護施設に入居して長期的な視野で生活全般を変えるのか?など様々です。
また、入院中でも明らかに介護が必要と判断できれば要介護認定を行う必要もあります。そういった場合は、病院の医療相談室、もしくは役所の介護相談窓口に相談して要介護認定に手続きを行います。

高齢者の入院に必要なもの
- 健康保険証
- 老人保健医療受給者証(75歳以上の場合)
- 診察券
- 入院申込書
- 印鑑
- 入院保証金(病院による)
- 寝巻
- 下着
- 靴下
- ガウン
- 洗面道具
- タオル類
- ティッシュ
- ウェットティッシュ
- スリッパ
- 食事用具
- ゴミ箱
- 筆記用具
- ビニール袋
- 小銭
入院中に介護が必要となったら
入院費用は思っている以上に高額です。そのため、完治するまで入院しているといったことも厳しい場合があります。
ですので、入院中に介護が必要となった場合は、退院後に困らないよう次のようなケースを事前に想定しておくといいかもしれません。
特別養護老人ホームへの入居
特別養護老人ホームとは、介護サービスの提供を主とする介護施設です。医療ケアは施設によって様々で、医療施設が隣接している所もあれば、提携病院があり必要に応じて医師が往診に訪れます。ですので、基本的な医療ケアは、常駐している看護師が行う場合がほとんどです。
医療ケアに不安はあるものの、レクリエーションやイベントは定期的に開催しているため、長期的な施設介護には適している施設といえます。
ただ入居基準が厳しく、2015年4月からは要介護認定で要介護3以上の高齢者となっています。また入居待ちが全国で50万人以上とも言われ、要介護度が高く早期の入居が必要と判断された高齢者から入居している状態です。

老人保健施設への入居
老人保健施設(老健)とは、医療法人や社会福祉法人などが運営する介護施設のことです。医療ケアやリハビリを必要とする重度な要介護状態の高齢者を受け入れています。
介護サービスは提供されるものの、治療やリハビリが目的の施設になるので、レクリエーションやイベントなどは行いません。
また、自立もしくは自宅で介護出来る状態まで回復すれば退去する必要があります。退去のタイミングに関しては、入居後3ヶ月ごとに様態の審査が行われ、退去可能と判断された退去の手続きが必要になります。
医療施設やリハビリサービスなどが受けられるとあって、特別養護老人ホーム以上に入居が難しいのが現状。入居基準も特養より厳しくなっています。

介護療養型医療施設への入居
介護療養型医療施設(療養病床)とは、医療法人が運営する医療施設で、特別養護老人ホームや老人保健施設では対応しきれず、医療ケアを必要とし重度な要介護状態の高齢者を受け入れている施設です。
基本的な介護は行いますが、あくまで医療を前提とした施設になるので、ターミナルケア(終末期介護)は行わず、様態が回復するまで病院に入院している状態が続くといった状態になります。
また、審査基準が厳しく空きも少ないため、老人保健施設と同様に入居するのが難しい場合がほとんどです。
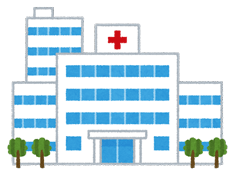
有料老人ホームへの入居
上記3施設と比較しても入居しやすく、介護サービスも充実しているのが有料老人ホームです。医療ケアに関しても、看護師はもちろん最近では医師を常駐させている有料老人ホームもあるようです。
介護と医療の両方のサービスが充実していて入居もしやすい有料老人ホームですが、どうしても入居にかかる費用は他の3施設と比べると高くなってしまいます。

在宅介護の検討
施設への入居が難しい場合は、自宅で介護を行うことになります。そういった場合は、まず地域包括支援センターに行き相談をして、ケアマネジャーを紹介してもらう必要があります。その上で、ケアプランの作成を行い、必要に応じてホームヘルパーや在宅医療サービスの利用を検討します。
同時に介護保険を利用して、介護福祉用具の購入やレンタルの手配であったり自宅の改修工事も行うといいでしょう。
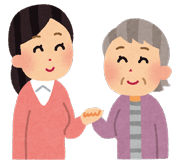
高齢者の病気は介護生活への宣告
繰り返しになりますが、体力も治癒力も衰えている高齢者にとって怪我や病気は介護生活への宣告だと思っていいほど重大なことです。
怪我や病気に関しては仕方がないといった部分も当然ありますが、未然に防げることでもあったります。
日頃の健康状態への配慮や適度の運動といった体力づくり、身の回りの整理整頓やバリアフリー化なども介護予防の一貫です。
「まだまだ元気だから」ではなく「もしかしたら危険かも」といった心がけも大切になります。
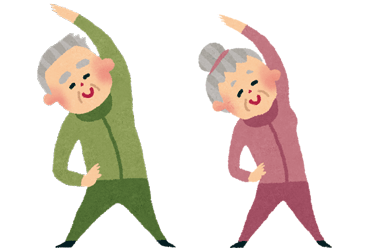
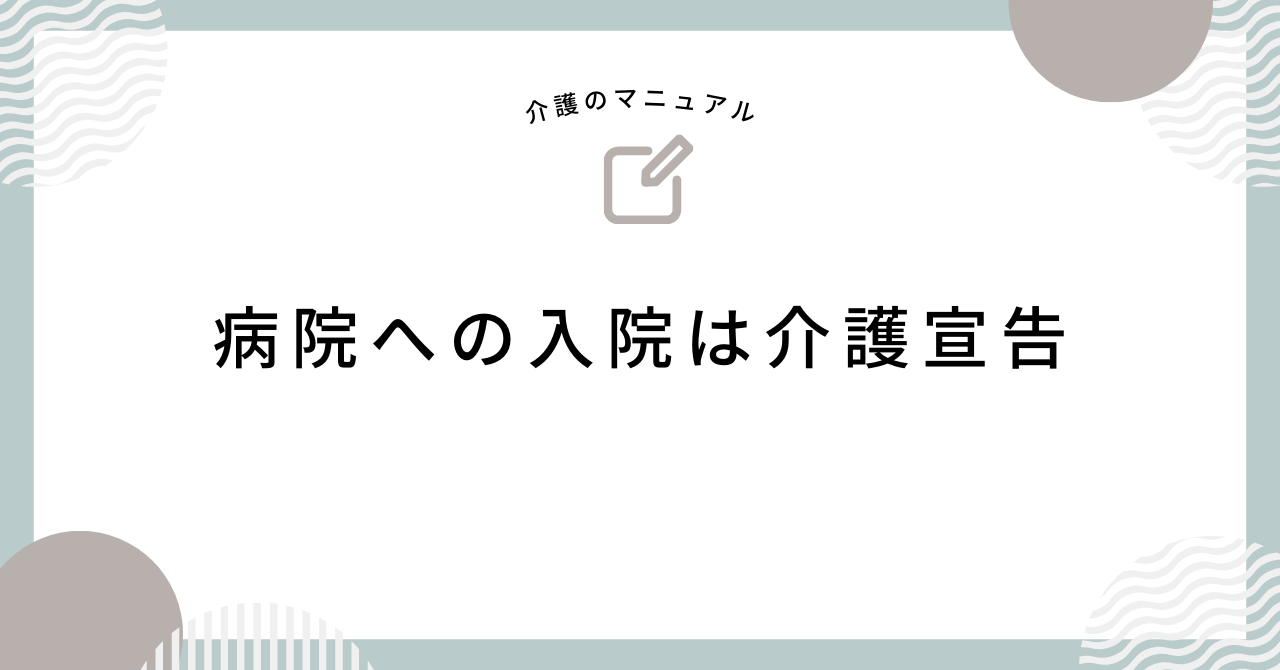

記事のコメント